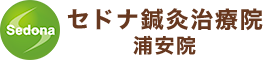東洋医学について①
浦安駅から徒歩1分セドナ鍼灸治療院の大谷です。
鍼灸とは中国に起源を持つ医療行為で、日本には6世紀のはじめごろに伝来したと言われている伝統的医療です。細い金属性の鍼(はり)をツボに刺したり、お灸を燃してツボに刺激を与えたりすることで、身体の不調や疾患の改善を目指します。あらゆる症状に効果があります。一例としては、腰痛や肩こり、関節痛や神経痛のほか、呼吸器系・循環器系の疾患、生殖系、婦人科系、耳鼻科系、運動器系などが挙げられます。これらの効果はWHOも適応疾患として公式発表しており、世界中で臨床的な効果も認められています。
とはいえ、鍼灸がなぜ効くのか、その仕組みを理解している患者さまが少ないように感じています。今回は、鍼灸の考え方やメカニズムについて、分かりやすく解説したいと思います。
東洋医学の発病のメカニズム
西洋医学が、病気の原因をウイルスなど体の外部にあると考えるのに対し、東洋医学では、体の内部環境の乱れが先にあると考えられています。体の内部の乱れによって病気になる、またはそれに乗じて外部環境邪気(ウイルスなど)が体に入りこみ、体から排除できない要因が重なると症状が現れる。この発病のメカニズムは、体のなかの①「邪気と正気」、②「陰と陽の失調」という二つの要因で説明されます。
- 邪気と正気
人体には「生気」と呼ばれる免疫力が備わっています。それが外から侵入してくるウイルスなどの「邪気」と闘うことで、邪気を撃退するときもあれば負けるときもあります。こうした相互作用は疾病の発生と発展に関わっているだけではなく、疾病の予後や転帰をも左右しています。疾病の発生~転帰とは、生気と邪気の闘いの過程でもあるのです。
特に生気が邪気に抵抗し防御する反応のことを「生気の抗邪反応」といいます。
- 陰と陽の失調
中国医学では陰陽失調により体のバランスが崩れると考えられています。人体の陰と陽の正常な関係が乱れると陰陽の偏盛偏衰があらわれ、五臓六腑や気血津液の機能も異常となり、発病の原因となるというわけです。
陰陽失調は基本的には二種類に分けられます。一つは有余で実証といい、もう一つは不足で虚証といいます。どちらも陰陽が相対的平衡を失ったものを指しています。
鍼灸でご自分のからだを守っていきませんか?
不安なことがありましたら何でもご相談下さいね。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 ブログ2024.07.222024年8月18日(日)健康セミナー開催!
ブログ2024.07.222024年8月18日(日)健康セミナー開催! お知らせ2024.07.15骨盤からくる身体の歪み
お知らせ2024.07.15骨盤からくる身体の歪み お知らせ2024.07.152024年8月スケジュール
お知らせ2024.07.152024年8月スケジュール お知らせ2024.07.15気圧による頭痛のメカニズムと対策
お知らせ2024.07.15気圧による頭痛のメカニズムと対策